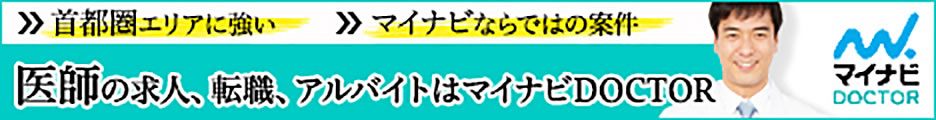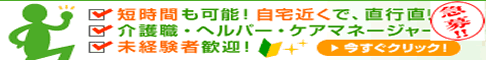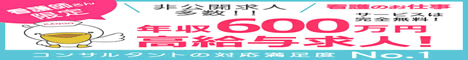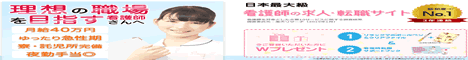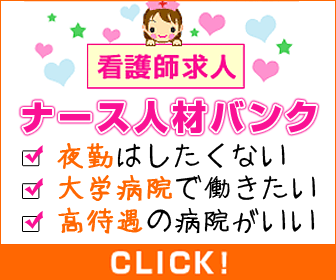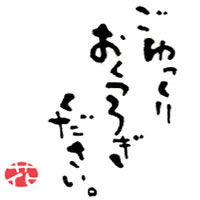イクメンという言葉が浸透し男性の育児参加が増えているといいますが、 現実に出産・授乳をするのは女性であり、女性が育児に割く時間は大きなものです。 女性が多い看護師にとって出産・育児のときに仕事をどうするのかは、今も昔も大きな課題になっています。
看護師は産後どのぐらいで仕事復帰しているのか、産休後の再就職で不安に思われる点や注意したいポイントについてまとめます。
■ 産後はいつから仕事復帰?
産休っていつからいつまで?
産休とは、産前休暇・産後休暇の略称であり、労働基準法では「6週間(多胎の場合14週間) 以内に出産予定の女性が休業申請した場合には受理すること」「産後8週間を経過しない女性を就業させないこと」と定めています。
つまり、産前産後で3ヶ月半の休暇をとることが法律で保障されているわけですが、 注目すべきは、産前の休暇取得は「申請があった場合」の決まりであって義務ではない、 という点であり、いつから休むかは定められていないのです。 同様に産後の休暇は2週間以上と決まっているものの、いつまでという法律はありません。
忙しい病院では、なかなか産休を言い出せない看護師もいることでしょう。 臨月になっても出産間際まで働いていたり、これが原因で妊娠高血圧症候群になって入院したという看護師もいるそうです。
臨月で働いていた先輩看護師がいるとそれが通例となってしまっている病院もありますが、 お産はひとそれぞれであり、休まなくても大丈夫な看護師も、休まなければ危険な看護師もいます。無理をするのはよくありません。
産休後の復帰時期は人それぞれ
法律で決まっている産後休暇期間の2ヶ月を過ぎれば、 子供を親や保育園に預けてすぐに看護師に復帰する方もいれば、半年〜1年など区切りの良いところまで休む方もいます。
さらに子育てを重視し、子供がある程度大きくなってからと考えて5〜10年程度のブランクがあく看護師もして、 同じ病院に復帰するのか転職するのか、その復帰時期もひとそれぞれです。
産休期間中の給与計算の仕方などは、就業規則に定められているのでしっかり確認しておきましょう。
産休後の看護師、再就職で不安なことは?
ブランクがあっても看護師仕事についていけるか、 3ヶ月程度の産休であればブランクはほとんど感じないかと思いますが、 半年、1年とブランクが増えるほど「看護師仕事についていけるだろうか」という不安が大きくなります。
日進月歩の医療現場ではどんどん新しい情報が更新されていき、処置方法が変わっていたり、 電子カルテへの移行があるかもしれません。看護師は、5年ブランクがあくと新人同様になるとも言われます。
これまで多くの看護師がブランクを乗り越えて復帰しているのですから、 必要以上に恐れる必要はないものの、ブランクの影響を覚悟して謙虚に学んでいく姿勢が大切です。
子供が体調を崩したとき
多くのワーキングマザーが最も不安に思うのはこの点でしょう。 乳児〜乳幼児の頃は体調を崩しやすく、急に高熱が出たりします。 保育園に預けていれば、看護中だろうとなんだろうとすぐにお迎えに行かなくてなりません。
そんなときには他の看護師に仕事を任せざるを得ず、人手が不足することに対し申し訳なく感じたり、 休みや早退が多くなると肩身が狭くなって「このまま看護仕事を続けていていいのだろうか」と思ってしまうことがあります。
スタッフの入れ替わり
転職の多い看護業界では、1年程度の産休でも何人ものスタッフが入れ替わっていることがあります。 働きなれた古巣に戻ってきたつもりが、知っている顔の方が少なかったという話も聞きます。
職場からすれば人手が多いに越したことはなく、面識のない看護師でも歓迎されるものですが、 復帰の前に仲のいいスタッフに相談しておくなどして、コミュニケーションの橋渡しをお願いするという方法もあります。
スポンサーリンク
■ 産休後の再就職で注意したいポイント
女性が働くことに対する理解は確実に広まりつつあり、院内託児所を設けたり、 時短勤務、フレックスタイム制を導入するなど、職場復帰・再就職を支援する方針の病院が増加しています。。
このようなサポート制度があったとしても、やはり産休後の復職は大変なものです。 大変さを少しでも減らせるよう、再就職の前に注意しておきたいポイントを確認しておきましょう。。
優先順位を考え、慣らし運転から
小さい子供を育てながら以前と同じように仕事をするというのは、 現実的に無理であることを受け止めましょう。「仕事も育児も頑張らなければ」 と責任感を強くもつほど、理想と現実とのギャップに疲れてしまいます。
子供は社会化の慣らし期間ですが、看護師自身も復帰の慣らし期間だと考えましょう。 仕事の優先順位を考えておき、発熱で早退する時には他の看護師に引き継げるよう、 いつも仕事を可視化しておいたり、連携関係を維持しておきます。
数年もすれば「あの頃は何だったのだろう」と思えるぐらい子供は丈夫になり、 自分の仕事のペースが出来てくるものです。看護仕事や生活の工夫をして、 前向きな気持ちで頑張ってみましょう。先輩のママ看護師に相談してみるのもいいですね。
病院のサポート体制を確認しておく
院内保育所があれば、発熱のときにもすぐに迎えに行けて助かります。 授乳時間制度を設けているところもあり、仕事中1日2回の授乳が認められていれば、昼休みと合わせて3回の授乳が可能です。
産休後は日勤のみの外来へ異動してもらったり、 日勤のみの転職先を探してみましょう。ブランクが心配なときには、復職支援制度・研修が充実している求人を探します。
求人情報に「ブランクのある看護師歓迎」と書かれていていても、 現実的には忙しく具体的な支援は出来ていないところもあります。 実際にどんな支援状況があるのかを確認するなら、転職サイトのエージェントに聞いてみるのがおすすめです。
夜間の授乳がある間は「昼間働いて夜も眠れなかったら体力が持つだろうか」 という不安があります。夜泣きの頻度は赤ちゃんによるので一概には言えませんが、 夜中のミルクはパパと1日おきの当番制にして乗り切った、という体験談もあります。
看護師仕事を客観的に見つめなおし、家族やスタッフのサポートを受けながらの再就職について、イメージしてみてくださいね。
|
看護師の子育て、育児休暇は取れるの?、まとめ ■ 産休は法律では3.5ヶ月だが、期間は自由に選ぶことができる。 ■ 復帰時期は2ヶ月〜数年と人それぞれです。 ■ ブランクやスタッフの入替え、子供の発熱時などが不安材料になります。 ■ 慣らし期間と考え、工夫しながら頑張ってみる。 ■ 院内保育や復職支援などのサポートがあるか確認します。 |
|---|
スポンサーリンク
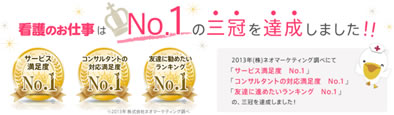
医師や看護師求人・転職の特典を徹底比較
医師や看護師・准看護師・助産師・保健師専門の転職、就職支援サービスです。 あなたのご希望条件をもとに、ご紹介します。 実績のあるキャリアコンサルタントから、無料で転職サポートが受けられます。 あなたの転職活動を強力にサポートします。 未公開求人情報なども多数ありますので、あなたのご希望にあった看護師求人がきっと見つかるでしょう。期間限定、転職支援金プレゼント。
▼ 看護師求人情報 よかったら参考にしてください。 ▼